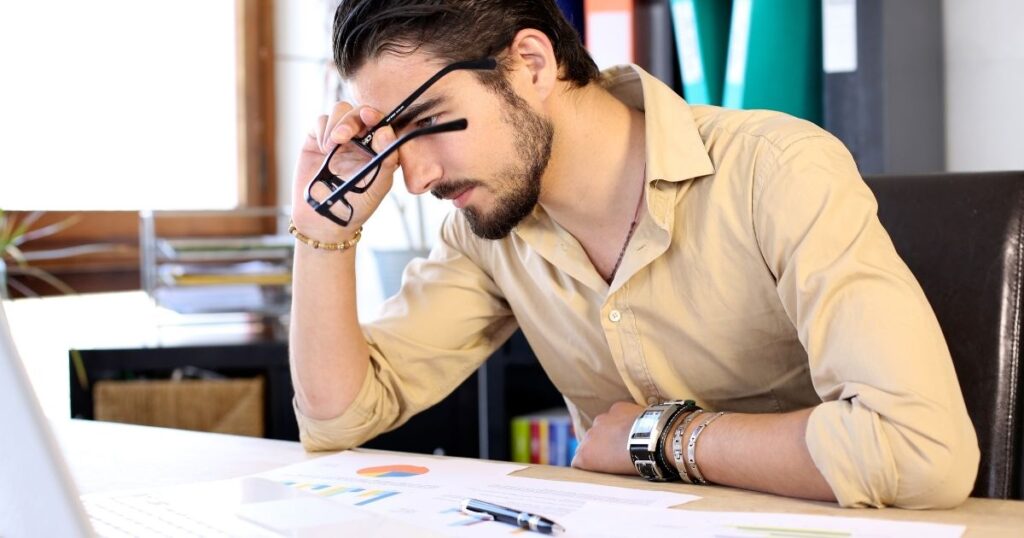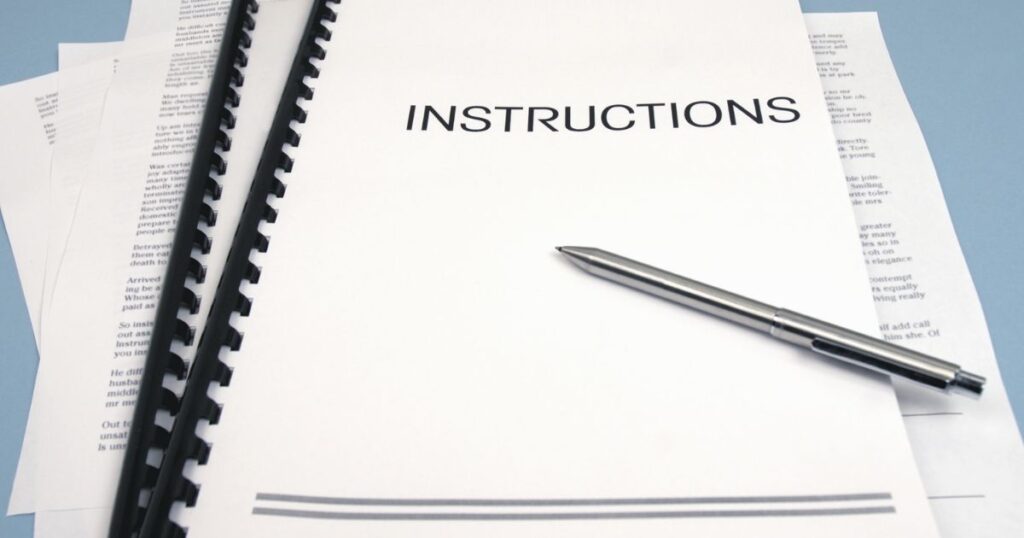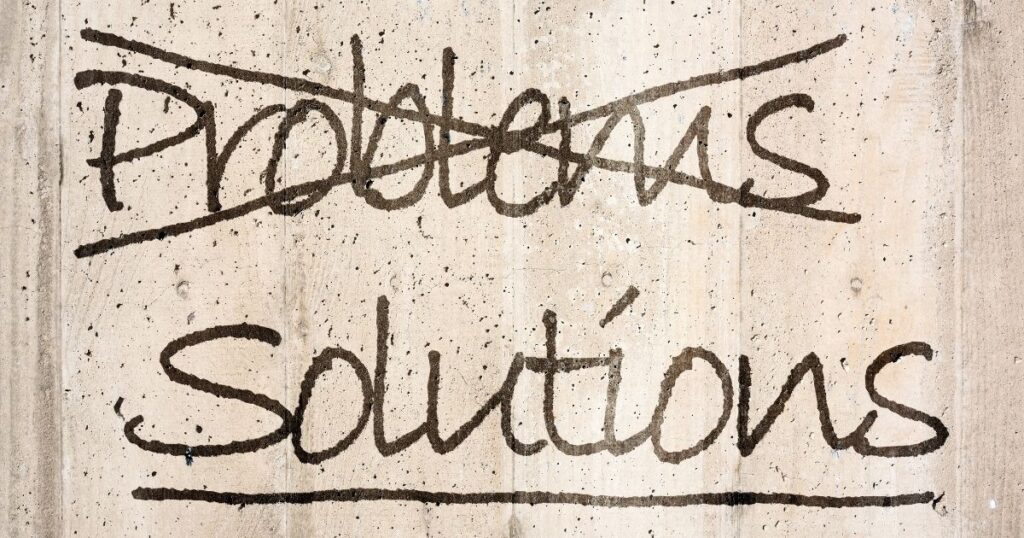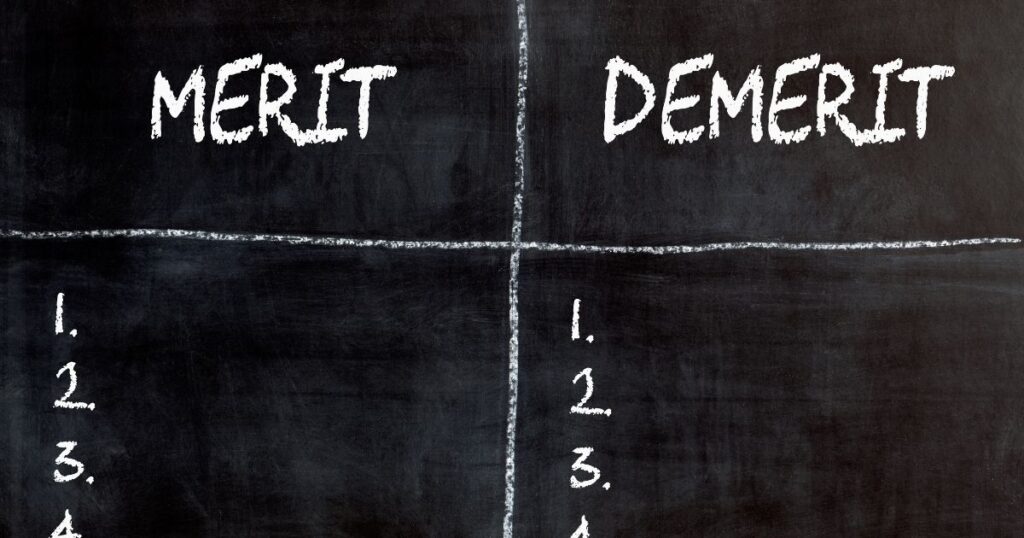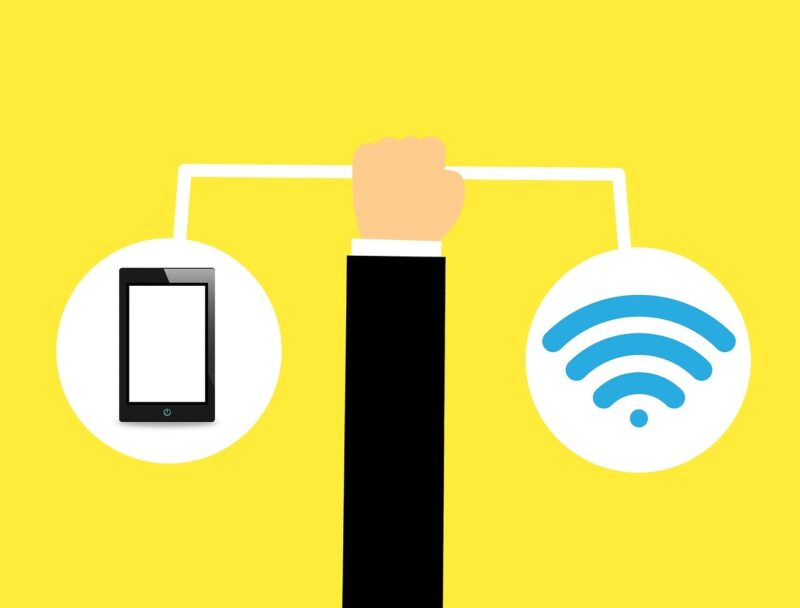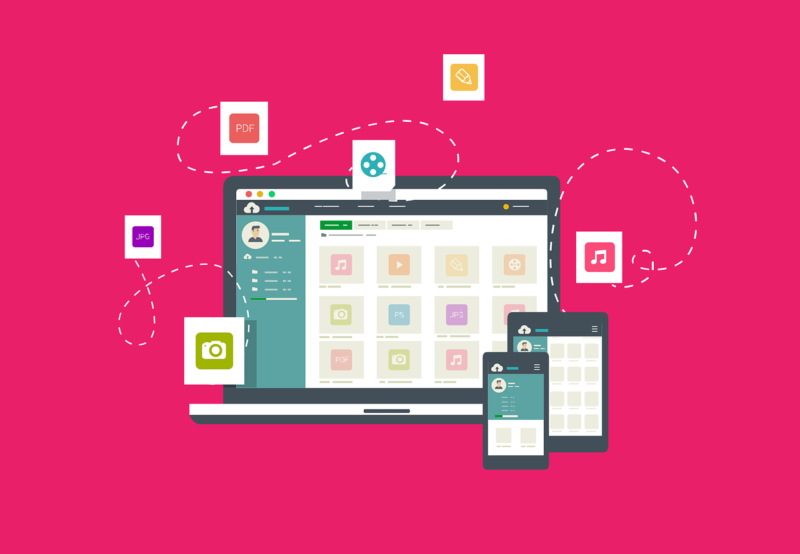テレワークとリモートワークの違いとは?在宅勤務との違いやメリット・デメリットも解説

新型コロナウイルスの影響により、人々の「働き方」も大きく変化していきました。その働き方の変化の代表的な例がテレワーク、リモートワークです。
そこで今回は、テレワーク、リモートワークの違い、特徴を中心に解説します。
両者の違いがいまいちよくわからない方は、ぜひ参考になさってください。
目次
テレワークとリモートワークの違いは?

結論、テレワークとリモートワークの大きな違いはありません。
テレワークはtele(遠く)+work(働く)、リモートワークとはremote(遠く)+(work)という意味で、どちらもオフィス以外で仕事をするという点では同じです。
したがって、在宅勤務はオフィス以外の場所で仕事をすることになるので、テレワークとリモートワークのどちらにも該当します。
<テレワーク・リモートワークはもちろん、出社時の勤怠管理も『RemoLabo』一つで大丈夫!多くの企業に選ばれるのには”理由”があります>
テレワークとリモートワークのメリットは?

テレワークとリモートワークの意味に大きな違いはありませんが、メリットは何なのでしょうか。以下で3つのメリットを解説していきます。
・コストの削減できる
・国の支援が受けることができる(地域による)
・社員のストレス削減
コストの削減できる
テレワーク、リモートワークを導入することで、会社のコストの削減ができます。例えば、現在新型コロナウイルスが流行していますが、各企業はテレワーク・リモートワークを推進しています。その結果、下記のコストが削減されました。
出張費用
事務所の設備費用
通勤費
上記は会社によって、違いはありますが大きなコスト削減としては、上記3つの通りです。特に、オフィス以外の場所で仕事をするとなると、通勤費がかかりません。通勤費も会社から遠くに住んでいる社員にとっては高い金額です。会社がその金額を負担するので、大きなコストになります。
テレワーク・リモートワークになると、通勤費が必要ないので、コスト削減が可能です。また、事務所も不在となるので、設備経費のコスト削減も可能となります。
国の支援が受けることができる(地域による)
地域によっては、テレワーク・リモートワークを推進すると、政府からの支援をすることが可能です。実際、NTTユーザー協会などが政府と連携し、テレワーク導入のための支援を行っています。
全国の中小企業を支援する団体(商工会議所、社会保険労務士会、NTTユーザー協会など)と連携し、テレワーク導入のための初期相談・問合せを受け付けております。
また、「テレワークの効果や全体的な導入方法についてまずは知りたい」といった方々向けに、セミナー・相談会も開催しています。
引用元:総務省「ICT利活用の促進」
もし、気になる点やテレワークやリモートワークを推進しようとしている場合は、一度相談してみてはいかがでしょうか。相談は、厚生労働省と総務省によるテレワーク相談センターから可能です。
社員のストレス削減
テレワーク・リモートワークは社員のストレス削減にもつながります。
・会社に出社する必要がない
・自分のペースで仕事ができる
・仕事場を自由にできる
会社に出社する必要がないのは社員にとって最大のストレス削減ではないでしょうか。
また、自分のペースで仕事ができ、自宅で仕事をしていて集中力が無くなった場合、カフェで仕事をしても何も言われません。
したがって、社員にとってテレワーク・リモートワークは場所や働きを選択できるので、ストレス削減にもつながります。
テレワークとリモートワークのでデメリットは?(解決策あり)

テレワーク・リモートワークは社員によっては魅力的な働き方ですが、当然メリットがあればデメリットもあります。
・周りに同僚・上司がいない
・自己管理が必要になる
・ITデバイスに弱い人は大変
周りに同僚・上司がいない
テレワーク・リモートワークで問題となるのは、周りに人がいないということです。つまり、仕事をしている際にわからない、判断が必要な案件がある場合にすぐに聞けないことがデメリットとなります。
そのため、気軽に相手に聞けるシステム(チャットできるITツール)などを導入しておきましょう。電話でも良いですが、資料を見ながら文章でフィードバックや意見をもらうことも大切です。したがって、電話とチャットできるITツールは導入しておきましょう。
自己管理が必要になる
在宅での仕事になると、自己管理が必要になります。つまり、自分に厳しくなくてはいけません。人間、家にいると誘惑が山ほどあります。そのため、ついつい仕事をサボったり、仕事の生産性も落ちたりする場合があります。
そのような状況を無くすため、下記を徹底していきましょう。
対応策
・1日のスケジュールを決める
・集中力が切れたら喫茶店など別の場所で仕事をする
・同僚とオンラインで一緒に仕事をする
1日のスケジュールは大切です。テレワーク・リモートワークになると、通勤する必要がないので、人は堕落します。したがって、何時に起きて、就寝するなどのスケジュールを作りましょう。
また、集中力が切れたら、場所を変えて仕事をするのも良いです。そして、同僚とオンラインでお互いを監視しあい、仕事をすることも良いのでないでしょうか。
ITデバイスに弱い人は大変
テレワーク・リモートワークを導入するにあたって、不可欠なのが「ITツール」です。ITツールなしでは、仕事や会議、同僚や上司ともコミュニケーションが取れません。
したがって、ITツールの仕様や使い方の説明やマニュアルを配布するなどの事前準備が必要になります。
基本的には下記のツールが使用頻度が高いです。
・ITチャットツール
・テレビ会議ツール
これらはテレワーク・リモートワークでは必須のITツールになるので、必ず使い方を頭の中に入れておきましょう。社内でITに強い人がいれば、ITキーマンとして、その人がマニュアルや説明会を開くのも良いのではないでしょうか。
テレワーク・リモートワークを導入する際は「社内打ち合わせ」が必要

上記でテレワーク・リモートワークのデメリットについて解説していきましたが、デメリットを無くす上で大切なのは「社内打ち合わせ」です。例えば、今からテレワーク・リモートワークを導入する際は、下記のことが大切になります。
・社員の理解
・ITツールの共有
・管理体制
・連絡方法
他にも様々なことがありますが、まず大切なのは「社員への説明と理解」です。テレワーク・リモートワークをするのは社員たちです。社員が何も分かっていないと、仕事になりません。したがって、社員が仕事をしやすい環境作りをしていくことが大切です。
前述したように、ITツールへの理解、管理体制や連絡方法は今までオフィスで仕事をしていた社員にとってイレギュラーになります。
テレワーク・リモートワークを実施する前は必ず、細部まで社員たちに理解してもらうように話し合って決めていきましょう。
会社だけでなく、家庭での「事前打ち合わせ」も必要

テレワーク・リモートワークを始めるにあたって、社内の事前打ち合わせは重要です。それと同様に、大切なのが家庭内での事前打ち合わせです。何故なら、働いている人にとって、家がオフィスになるからです。1人暮らしであれば問題ありませんが、家にパートナーや子供がいる場合は話が変わります。
当然、ライフスタイルも変わってきます。例えば、以下のことが変化していきます。
・仕事場の確保
・食事の調達
・家庭内のルール
・子供との距離
仕事場が家になるので、仕事をする場所の確保が必要になります。
そして、重要なのは家庭内のルールです。普段、オフィスで働いている人にとって、家にいないので、家のルールがわからない場合があります。また、家がオフィスになるので、パートナーとどのように仕事と家庭を両立していくかルールを作る必要があります。
昨今では「コロナ離婚」、つまりテレワーク・リモートワークが原因で別れるケースも少なくありません。特に、子供がいたら仕事をしつつ、家庭を見ることも大切になってきます。したがって、テレワーク・リモートワークが導入される際は、必ず家庭やパートナーと話し合いを設けましょう。
テレワーク・リモートワークの違いに大差はない

前述したように、テレワーク・リモートワークの違いに大差はありません。業種によって、言葉が異なる場合もありますが、基本的には同じ意味です。
ここでおさらいをしていきましょう。
テレワーク:一般企業、政府系企業が使用
リモートワーク:IT企業、フリーランスの人たちが使用
メリットはコストを削減でき、従業員のストレスを減らすことができる
地域によっては、国から助成金を得ることができる
デメリットは社員の自己管理と、ITツールの導入の必要性
テレワークという働き方が一般的となる過渡期ともいえる今の状況をチャンスに変えて、変えれる部分は変えていきましょう。上手くいけば、会社にとっても大きなプラスになるはずです。
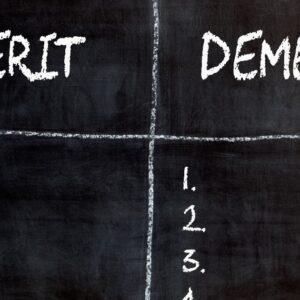
【始める前に知っておくべき】テレワークのメリット・デメリット
この記事では、在宅勤務の未経験者やテレワークの導入を検討している事業主の方に向け、テレワークのメリット・デメリットを企業側・従業員側それぞれの視点で検証し、課題解決方法を…

テレワークとはどんな働き方?テレワーク導入に悩むあなたに向けて解説!
テレワークは昨今、企業にとって欠かせない働き方となりました。特に、2019年の政府が行った「働き方改革」で、テレワークは急速に企業に普及してきました。そして、2020年に…

【実は概念が違う!】テレワークと在宅勤務の違いをイチから解説!
テレワークと在宅勤務の違いとは?【Remotework Labo】ではテレワークと在宅勤務について知りたい方に向けて、両者の違いやメリット・デメリットを解説しています。テ…