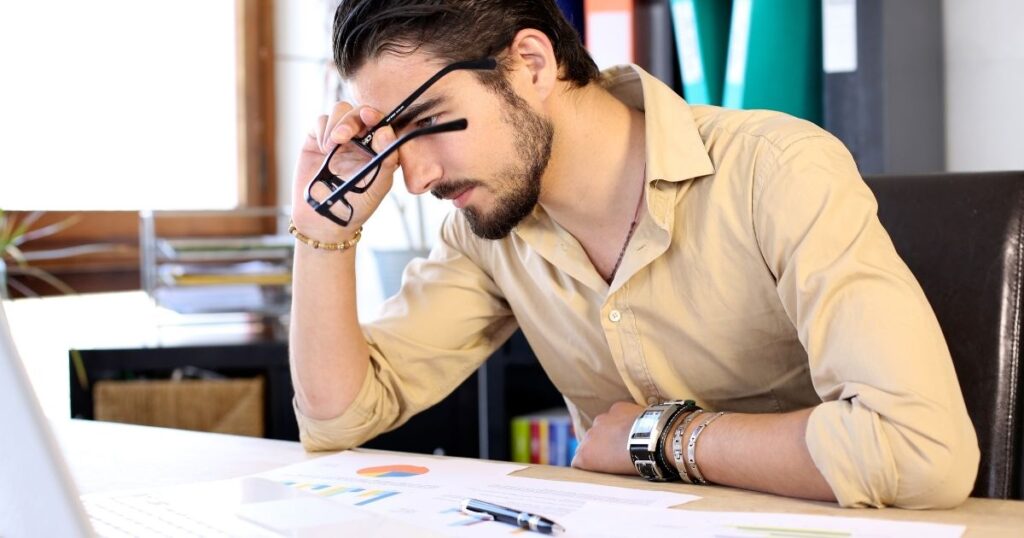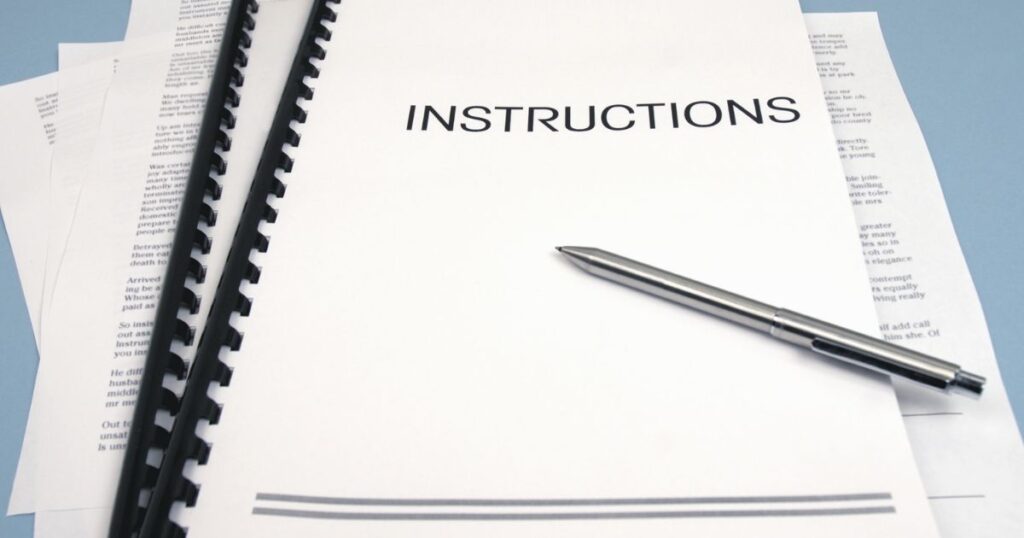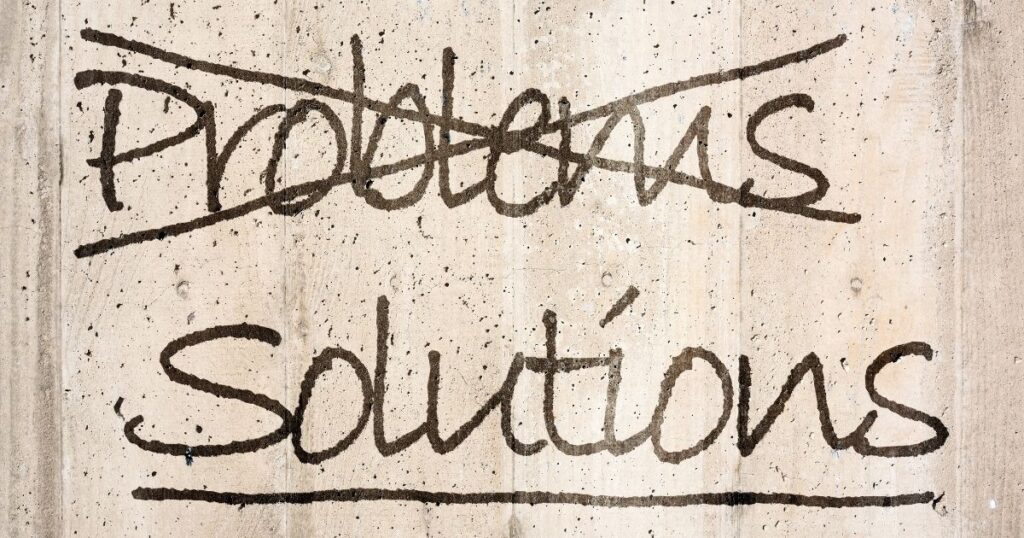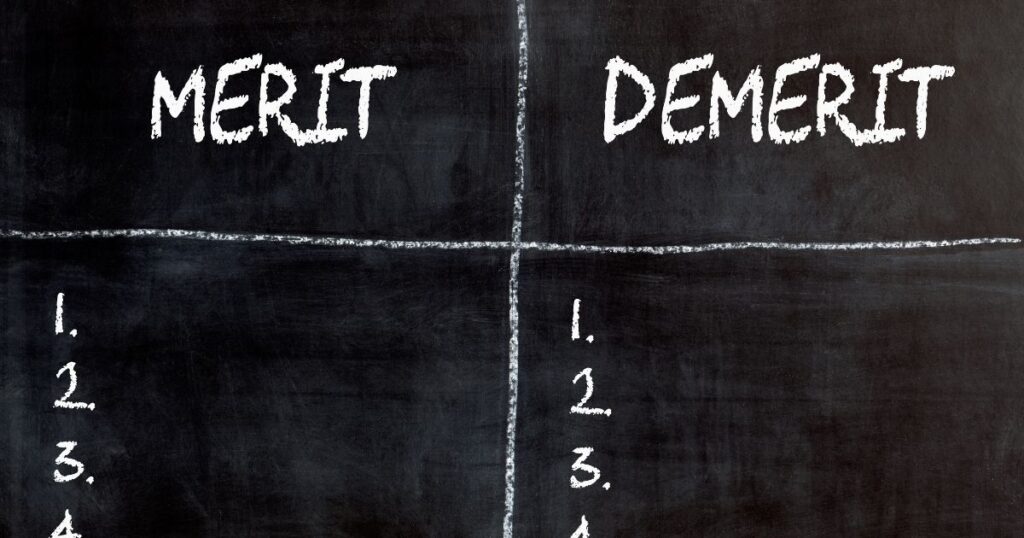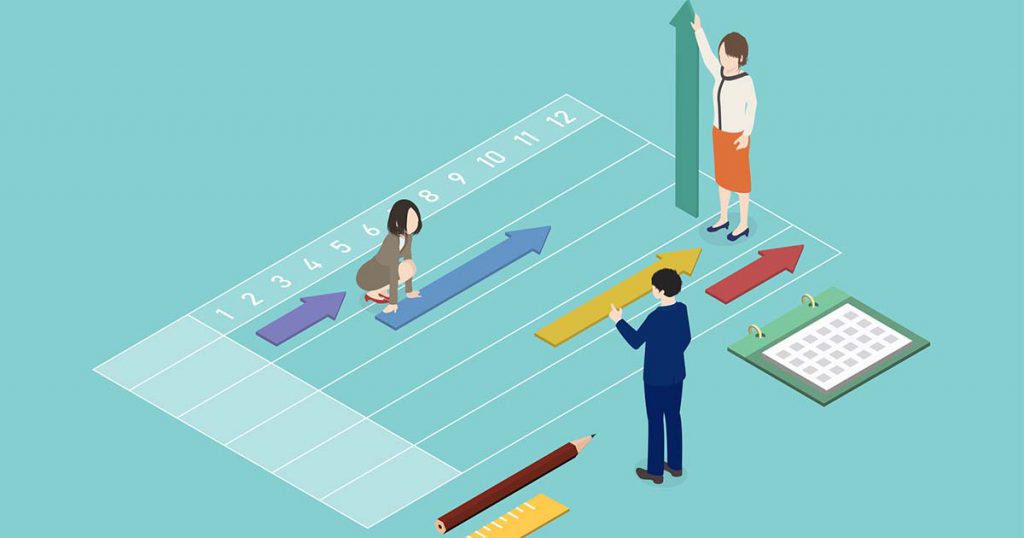コア業務とノンコア業務の違いとは?定義やアウトソーシングについて解説

企業の利益を上げるためには、コア業務に力を入れなくてはなりません。しかし、ノンコア業務が滞っていると、肝心のコア業務にも影響を及ぼしてしまうでしょう。
そこで今回は、ノンコア業務とは何なのかを解説します。また、ノンコア業務のアウトソーシング方法も見ていきましょう。
コア業務とノンコア業務の定義
コア業務とノンコア業務の概要を簡潔にご紹介します。
コア業務とは
コア業務とは、その企業の主要な収益源であり、その企業のアイデンティティやブランドを形成する上で重要な活動や業務のことを指します。コア業務は企業が他の競合と差別化を図るための基盤となり、長期的な成功と成長の鍵となります。
たとえば、自動車メーカーのコア業務は自動車の設計、製造、販売であり、IT企業の場合はソフトウェアの開発やクラウドサービスの提供がコア業務になります。
ノンコア業務とは
ノンコア業務とは、会社の利益に直接かかわらない業務のことです。一般的な企業では、事務、経理、秘書、総務などのコア業務を支える部署が該当します。
ノンコア業務とコア業務の違い
上記の通り、直接利益につながらないノンコア業務に対して、利益に直接つながる業務のことをコア業務と呼びます。主に営業活動や商談、経営企画や市場調査などがコア業務に含まれます。
コア業務は高度な判断を要するものも多いのが特徴です。
企業の利益を上げる業務の考え方
企業が利益を上げるためには、コア業務に集中することがとても大切です。そのためには、まず業務内容を整理し、コア業務とノンコア業務に分け、ノンコア業務については適宜アウトソーシングを導入して効率的に処理できるよう体制を整えましょう。
<重要なコア業務だからこそリモート中もRemoLaboで進捗を確認!機能の詳細はこちらから>
ノンコア業務のアウトソーシングについて

ノンコア業務をアウトソーシングすることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ノンコア業務をアウトソーシングするメリット
一部の業務をアウトソーシングすることによって従業員がコア業務に集中でき、効率化も図れるうえ生産性が向上します。また、新たな人材を雇うための採用コストや福利厚生費などの人件費も抑えられます。
アウトソーシングの種類について
3種類のアウトソーシングについて解説します。
<PUSH OUT(プッシュアウト)型>
PUSH OUT型は、主に単一のノンコア業務を外部委託します。コア業務と切り離すことで、業務の効率化と費用削減が見込めるでしょう。
<ADD ON(アドオン)型>
PUSH OUT型に加えて、納期の短縮や質の向上を期待できるのがADD ON型のアウトソーシングです。
<BUY IN(バイイン)型>
BUY IN型のアウトソーシングは、ノンコア業務の枠にとどまらず、新たな価値や品質の向上も見込めます。
まとめ
コア業務に集中することは会社の利益を上げるために大切ですが、コア業務自体がノンコア業務に支えられていることも多いため、結局企業にとってはどちらも重要です。
アウトソーシングで対応可能だからといってノンコア業務の重要度が落ちるわけではないので、この点は留意しておきましょう。
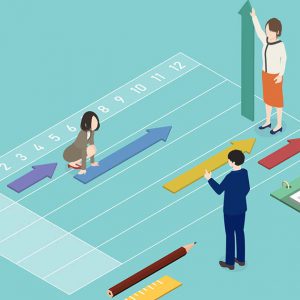
テレワークにおける目標管理の必要性とは?有効的に活用するコツや問題点の解決策についても紹介
目標管理を取り入れている企業は少なくありませんが、うまく活用できなければ効果が半減してしまうため、有効的に活用する方法を理解することが大切です。 ここでは、目標管理の必要…

【少しの工夫で仕事できる人に!】テレワークに向いている人の性格や職種、対策を解説!
コロナ後の新しい働き方として、テレワークなどの在宅勤務を導入する企業が増えてきました。 そんな中、テレワークをこれから始める人や始めたばかりの人にとっては、「一人で作業す…

テレワークの人事評価は難しい?課題点やポイントを解説
リモートワークでは従業員の働きぶりをどう評価すれば良いのか、正当に評価してもらえるのか、評価者も被評価者も悩んでしまうものです。 そこで、ここではテレワーク中の人事評価の…