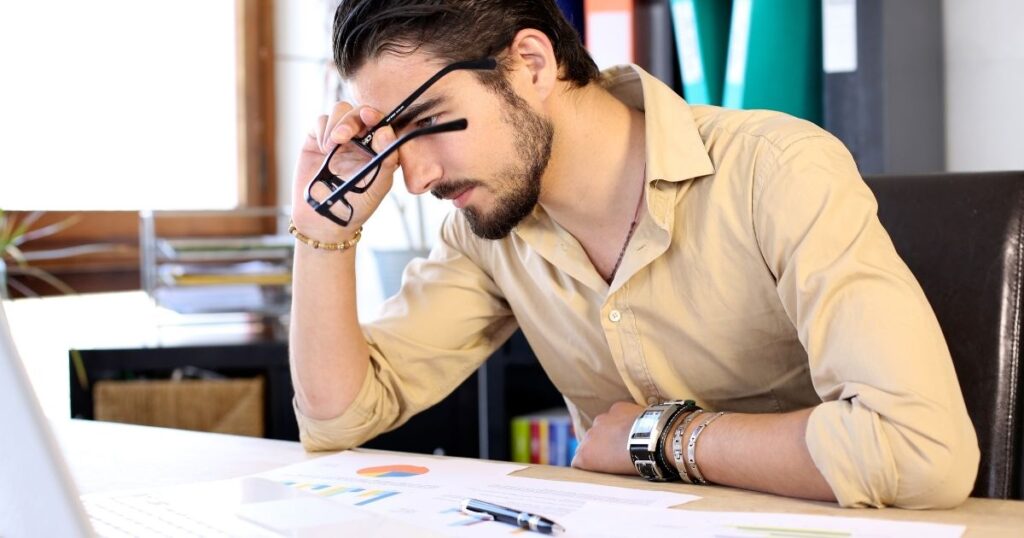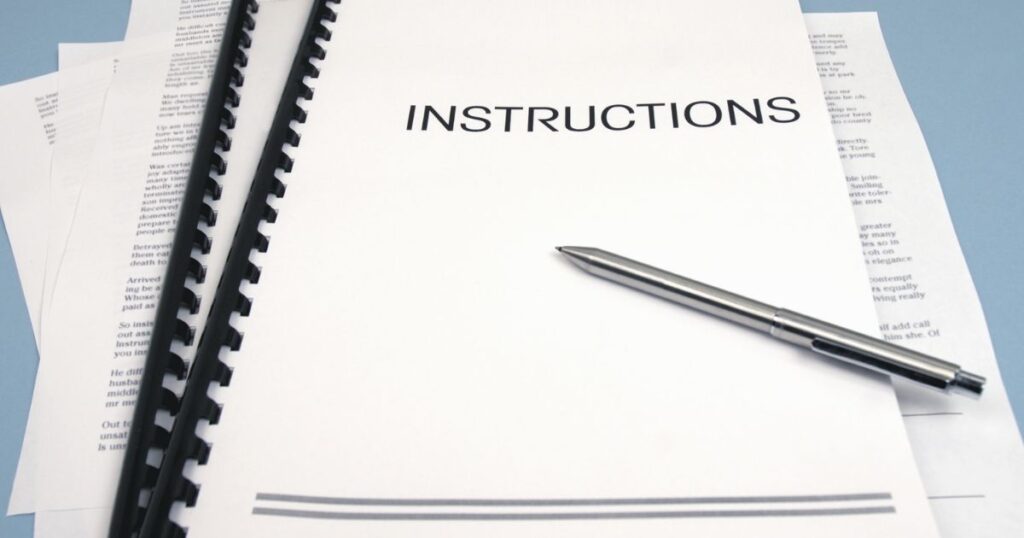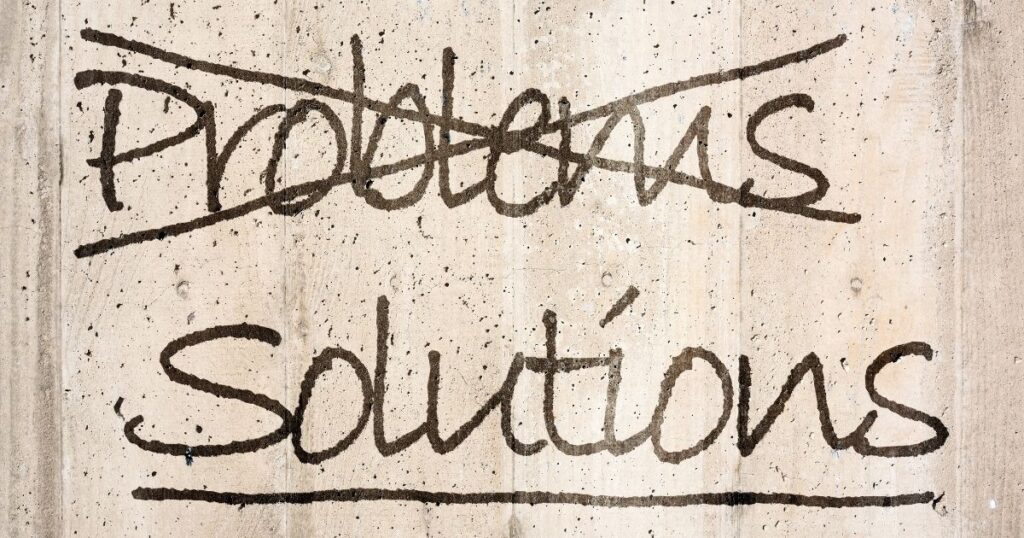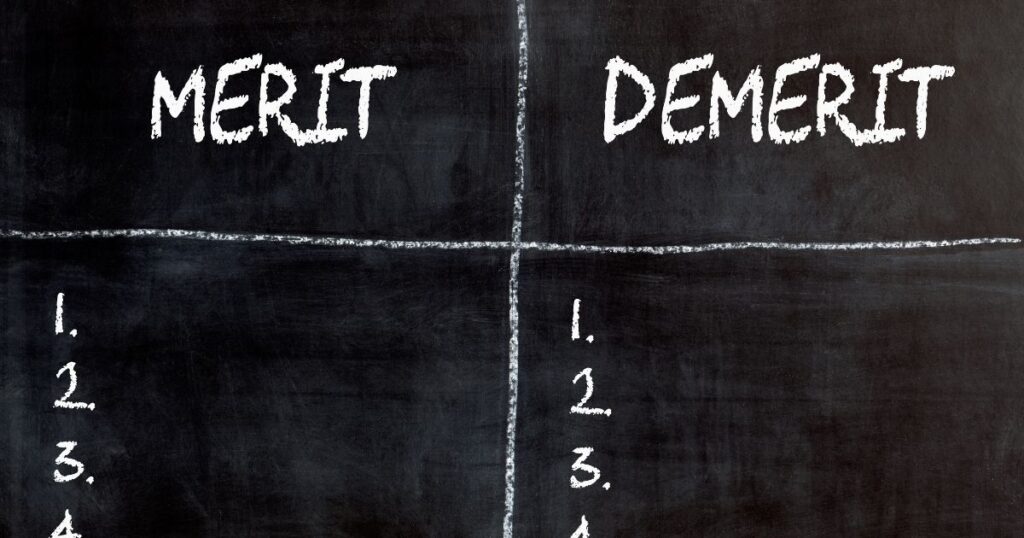テレワークにおける目標管理の必要性とは?有効的に活用するコツや問題点の解決策についても紹介
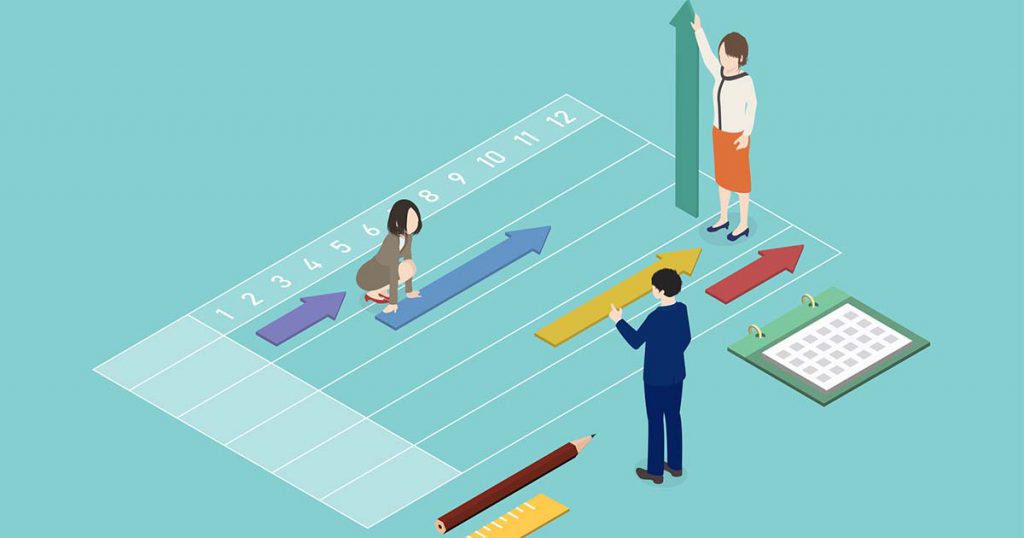
昨今、目標管理を取り入れている企業は少なくありませんが、うまく活用できなければ効果が半減してしまうため、有効的に活用する方法をしっかり理解することが大切であり、それはテレワークを導入している場合でも同じです。
そこで今回は、テレワークでの目標管理の必要性や問題点を解決するための方法も紹介します。
目標管理について
目標管理とは、従業員が自ら目標を設定し、達成に向けて努力することで自主性や積極性を育みながら、会社への貢献につなげていく組織マネジメント手法の一つです。
従業員自身が目標を定めることで自己成長を促すとともに、従業員一人ひとりの生産性の向上や人事評価の効率化も期待できるといわれています。
テレワークにおける目標管理の必要性
リモートワークを導入している企業では従業員の働きぶりが見えず、直接的なコミュニケーションの機会が激減するため、導入していない企業に比べて目標管理の必要性はさらに高まります。
具体的には次のような点で目標管理の必要性を認識できるでしょう。
自己管理の強化
テレワークでは、従業員が自らの時間を管理し、自律的に作業を進める必要があります。明確な目標が設定されていると、従業員は何を達成すべきか、そしていつまでに達成すべきかを理解しやすくなります。
コミュニケーションの向上
リモートワークではチームメンバー間のコミュニケーションが物理的なオフィス環境よりも難しくなることがあります。しかし、目標管理を通じて、チームメンバー全員が共通の目標に向かって努力していることを確認し、進捗状況を共有することができます。
生産性の維持と向上
明確な目標と期限があることで、従業員はモチベーションを保ちやすくなり、生産性の維持や向上につながります。また、目標達成に向けた進捗を定期的に確認することで、必要に応じて計画を調整することができます。
成果の測定
目標管理は、テレワークでの成果を測定するための判断基準となります。これにより、従業員のパフォーマンス評価が公平かつ透明に行われるようになります。
目標管理を有効的に活用する方法

目標管理のしっかり機能させるためには、設定する目標と企業の目標に関連性が必要です。
従業員の役割が企業戦略へどのようにつながり、貢献するかを明確にすることで、携わっている業務が自身の成長へつながっている意識が芽生え、モチベーションが向上します。
<リモートワークで目標管理するならICTツールで業務プロセスもチェックを!リモート中の働きぶり・生産性を確認するなら『RemoLabo』で。>
目標管理で起きてしまう問題点
目標管理で目標の設定・面談・フィードバックが形骸化してしまうケースでは、従業員は目標設定時に達成しやすい目標を立てることが多く、上司は面談で達成率を重視してしまいがちです。
すると結果的にありきたりな目標を達成し、成長を感じられないまま次の目標設定の際にも同じようなことを繰り返す悪循環となってしまいます。
目標管理を形骸化させないためにすべきこと
目標管理を形骸化させないためには目標管理制度の担当者を決め、体制を整えることが必要です。従業員が自発的に立てた目標と、上司が企業の経営を反映した目標を組み合わせながら、いつまでにどのような方法で目標を達成するか検討しましょう。一方的に評価・指導される目標ではなく、従業員自ら行動できる目標にできればベストです。
まとめ
テレワークにおいても目標管理を適切に取り入れることで従業員がスキルアップできるとともに、企業側も事業の目標達成や成長力の維持・向上を実現できるメリットがあります。形骸化してしまう場合は、従業員自らの目標と会社の経営方針をすりあわせて、従業員をサポートしながら目標管理制度を運用していきましょう。

人事考課とは?注意点や手順などについてご紹介
人事考課は多くの企業で導入されており、従業員の仕事を評価することで成長を促すことやモチベーションを高めるためにも必要だと考えられています。今回は、人事考課の意味や目的、注…

働き方改革の取り組み内容と導入するメリット・デメリットとは?
働き方改革は企業規模を問わず多くの企業で大きな課題の一つとされていますが、主にどんな取り組み内容があるかご存知でしょうか。 ここでは、働き方改革の意味や取り組み内容、導入…

コア業務とノンコア業務の違いとは?定義やアウトソーシングについて解説
企業の利益を上げるためにはコア業務に注力する必要がありますが、ノンコア業務が滞っていると肝心のコア業務にも影響を及ぼしてしまうでしょう。 ここでは、ノンコア業務とノンコア…