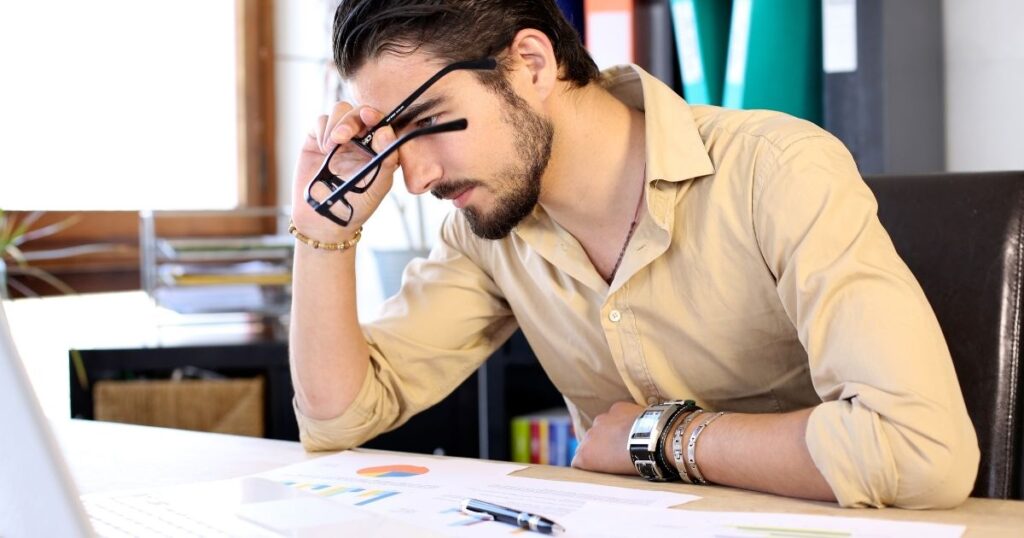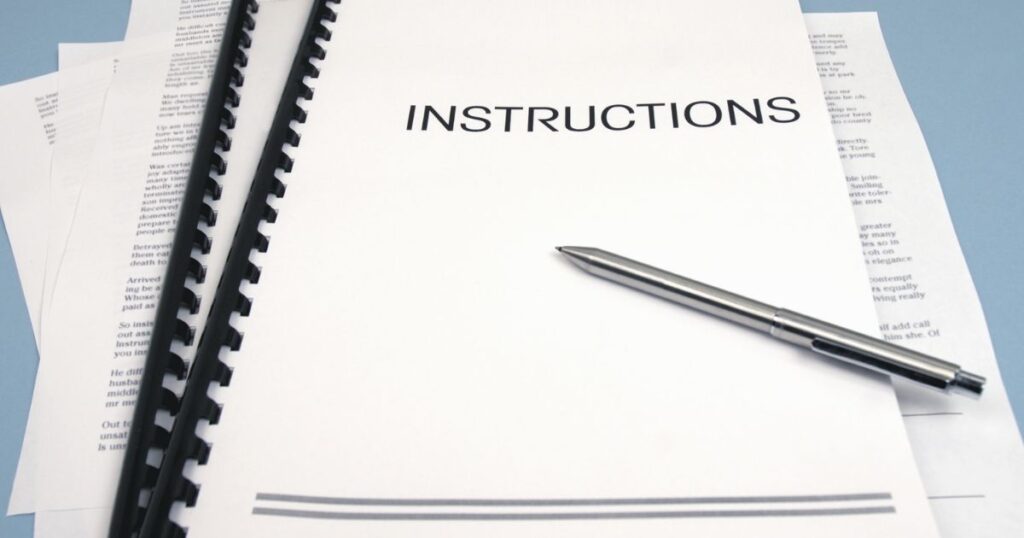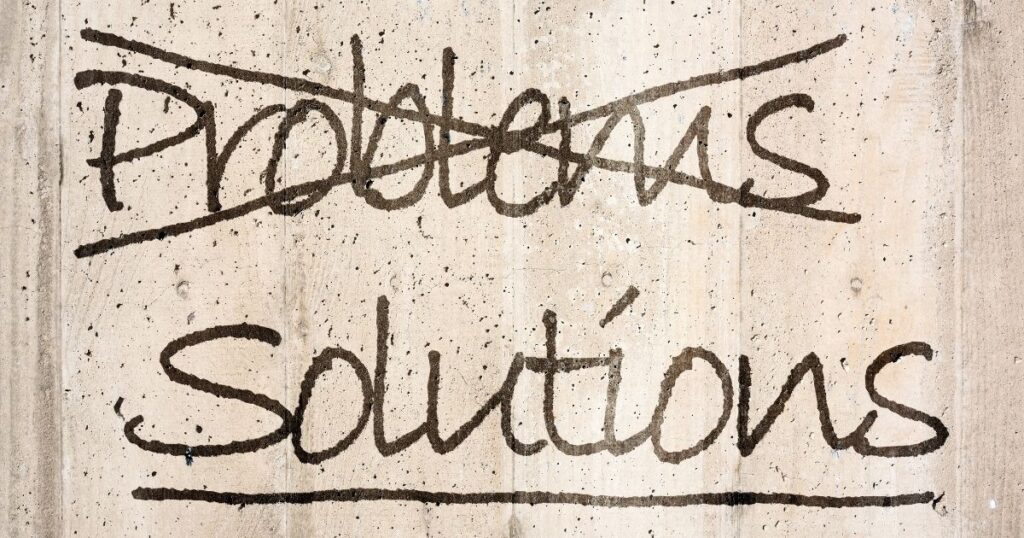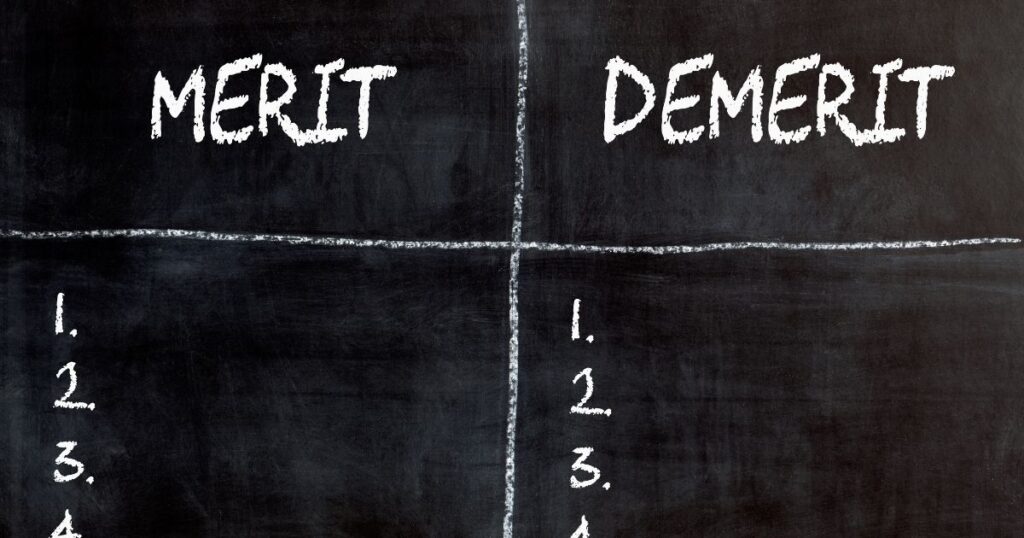勤怠管理の適切な方法とは?勤怠管理のルールについても紹介

勤怠管理には法律上のルールがあり、企業と労働者を守るうえでとても重要なものです。そのため、双方が勤怠管理について深く知る必要があります。
そこで今回は、適切な勤怠管理の方法についてご紹介します。
適切な勤怠管理について
正しい勤怠管理を行ううえで管理すべき項目や、厚生労働省のガイドラインの内容などをご紹介します。
そもそも勤怠管理で管理する項目とは?
労働基準法には、勤怠管理の管理項目に関する規定がありません。ただし、厚生労働省のガイドラインでは始業・終業時間を労働日ごとにチェックし、記録するものとされています。
厚生労働省のガイドラインによる勤怠管理の方法
厚生労働省のガイドラインでは、担当者がタイムカードやICカード、パソコンの使用時間などで勤怠状況を確認・記録する方法を推奨しています。その他、従業員の自己申告による措置も認められています。
自己申告制による勤怠管理について
自己申告が認められるのは、やむを得ないと判断される場合のみに限られます。労働時間の管理が曖昧になりやすい自己申告制がメインになると、不正申告につながりかねません。
<リモートワークの勤怠管理、まだ自己申告させていますか?勤怠管理ツール『RemoLabo』ならPC起動だけで始業時間がわかる!だから正確で不正も起きません>
勤怠管理での法律上のルールとは

適切な勤怠管理を行うために、勤怠管理における法律やルールをご紹介します。
労働時間について
労働基準法では、従業員の労働時間を1日あたり8時間、1週間で40時間までと定めています。規定の賃金内で労働させる場合、この基準を超えてはいけません。40時間を超えた部分は残業とみなされ、残業代を支払う必要があります。
労働時間の把握方法について
働き方改革関連法では、タイムカードやICカードによる打刻、パソコンの使用時間などの客観的な記録が該当すると規定されています。企業側には適切に労働時間を管理できる仕組みの構築が求められるでしょう。
年次有給休暇の取得について
働き方改革法案によると、企業は従業員に年間5日以上の有給を取得させることが義務付けられています。10日以上の有給がある従業員が対象のため、アルバイトやパートも含まれます。
賃金について
万が一残業が月間60時間を超えた場合、対象者に50%以上の割増賃金を支払うことが義務化されています。なお、残業時間が大幅に増えると過労死ラインを超える恐れがあるため、適切に管理しましょう。
まとめ
サービス残業や長時間労働を防止するためにも、勤怠管理は法律やルールに従い、適正に運用することが求められます。始業・終業時間はもちろん、休暇もしっかりと管理し、法律違反が起こらないように注意しましょう。

打刻ミスを減らす方法とは?原因と防止策を紹介
打刻は労働時間を正しく把握するために必要な作業ですが、打刻をし忘れる”打刻ミス”はどうしても一定の割合で起きてしまうもの。 そこで今回は、打刻ミスの原因と防止策をご紹介し…

勤怠管理に必要な勤怠表とは?期間や保管についても紹介
勤怠管理に欠かせない勤怠表ですが、作成・記録・保管は法的義務であり、これらを怠った場合は罰則が科せられるのをご存知でしょうか。 そこで今回は、勤怠表の目的や必要項目、保管…

リモートワークの勤怠管理はどうする?
リモートワークが以前より普及している一方で、勤怠管理に悩んでいる企業担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。今後リモートワークを導入しようと考えている企業は、どのよ…